逆数学:定理から公理を「証明」する電子ブック無料ダウンロード
逆数学:定理から公理を「証明」する (日本語) 単行本 – 2019/2/9
数学, 数学一般関連書籍, 川辺 治之
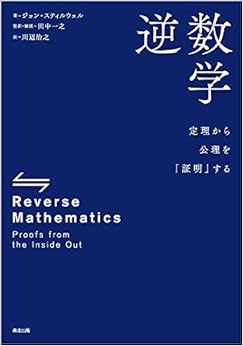
によって 川辺 治之
5つ星のうち3.9 5つ星のうち 8個の評価 人の読者
ファイルサイズ : 28.99 MB
「定理の証明には、いったいどれくらいの公理が必要なのだろう<?/b>」<; br>――古くは紀元前から、数学にはたびたびこの疑問が投げかけられてきた。この疑問にある種の回答を与えるのが、逆数学とよばれる数学基礎論の一分野である。逆数学では、"公理"から"定理"を導く通常の数学とは異なり、"定理"に必要な"公理"を探る。これによって、定理どうしを"深さ"で分類したりすることができる。たとえば、「最大値の定理は中間値の定理より"深い"」といった具合だ。本書では、解析学の基礎を通して、逆数学の基本的な考え方を解説。要所要所で歴史的な話題にも触れながら、読者をナビゲートしていく。本書を読み終えた後、読者は、これまで出会ってきた定理たちを少し違った角度から眺めている自分に気づくはずだ。「数学者は、材料の公理を加工して、定理という製品をつくり出す機械みたいなものか、といえば決してそうではないだろう。むしろ、ある定理を生み出すためにはどんな概念や仮説が必要か、あるいは、どうすればもっと少ない仮定で同じ定理が導けるかと考えていることが多いはずである。そのような(…)数学の内側(inside)を探る方法はないだろうか。この素朴な疑問に対して、内視鏡のような強力な道具を与えるのが逆数学なのである。」(監訳者解説より)◆電子版が発行されました◆詳細は、森北出版Webサイトにて◆【目次】はじめに 第1章 逆数学に至る歴史 1.1 ユークリッドと平行線の公理 1.2 球面幾何学と非ユークリッド幾何学 1.3 ベクトル幾何学 1.4 ヒルベルトの公理 1.5 整列順序と選択公理 1.6 論理学と計算可能性 第2章 古典的算術化 2.1 自然数から有理数へ 2.2 有理数から実数へ 2.3 Rの完備性 2.4 関数と集合 2.5 連続関数 2.6 ペアノの公理 2.7 PAの言語 2.8 算術的に定義可能な集合 2.9 算術化の限界 第3章 古典的解析学 3.1 極限 3.2 極限の代数的性質 3.3 連続性と中間値 3.4 ボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理 3.5 ハイネ-ボレルの定理 3.6 極値定理 3.7 一様連続性 3.8 カントル集合 3.9 解析学における木構造 第4章 計算可能性 4.1 計算可能性とチャーチの提唱 4.2 停止性問題 4.3 計算的枚挙可能集合 4.4 解析学における計算可能列 4.5 計算可能な道をもたない計算可能な木構造 4.6 計算可能性と不完全性 4.7 計算可能性と解析学 第5章 計算の算術化 5.1 形式体系 5.2 スマリヤンの初等形式体系 5.3 正整数の表記法 5.4 チューリングによる計算の分析 5.5 EFS生成集合に関する演算 5.6 Σ01集合の生成 5.7 Σ01関係に対するEFS 5.8 初等形式体系の算術化 5.9 計算的枚挙の算術化 5.10 計算可能解析学の算術化 第6章 算術的内包公理 6.1 公理系ACA0 6.2 Σ01と算術的内包公理 6.3 ACA0における完備的な性質 6.4 木構造の算術化 6.5 ケーニヒの補題 6.6 ラムゼイ理論 6.7 論理学からのいくつかの結果 6.8 ACA0の中のペアノ算術 第7章 再帰的内包公理 7.1 公理系RCA0 7.2 実数と連続関数 7.3 中間値の定理 7.4 カントル集合再訪 7.5 ハイネ-ボレルの定理⇒弱ケーニヒの補題 7.6 弱ケーニヒの補題⇒ハイネ-ボレルの定理 7.7 一様連続性 7.8 弱ケーニヒの補題⇒極値定理 7.9 WKL0の定理 7.10 WKL0,ACA0,そしてその先 第8章 全体像 8.1 構成的数学 8.2 述語論理 8.3 さまざまな不完全性 8.4 計算可能性 8.5 集合論 8.6 「深さ」の概念 参考文献 監訳者解説 索引
Komentar
Posting Komentar